「声は聞こえるのに、意味が分からない」
「静かな場所ならなんとかなるけれど、騒がしくなると何も聞き取れなくなる」
これは、感音性難聴の私が日々感じている困りごとです。
実はこの感覚、LiD/APD(聞き取り困難症/聴覚情報処理障害)と呼ばれる症状の特徴でもあります。
最近ではメディアやSNSでも少しずつ知られるようになってきたLiD/APD。
私はLiD/APDではなく難聴ですが、症状や日常の困りごとに強く共感できる部分がたくさんあります。
今日は、LiD/APDと感音性難聴の「似ている部分」と「違う部分」についてお話しします。
LiD/APDとは?
[聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder: APD)とは、
「聞こえている」のに「聞き取れない」、「聞き間違いが多い」など、音声をことばとして聞き取るのが困難な症状を指します。通常の聴力検査では異常が発見されないこの症状は、耳から入った音の情報を脳で処理して理解する際に、なんらかの障害が生じる状態だと考えられています。]
(出典:「LiD/APDって何?」│聞き取り困難症・聴覚情報処理障害(LiD/APD)当事者ニーズに基づいた診断と支援の手引きの開発)
海外では、LiD(Listening Difficulties)という表現が使われることもあります。
つまりLiD/APDは、「聞こえているけれど、聞き取れない」——聞き取りに困難を感じている状態を指す言葉です。
LiD/APDと難聴の違い
両者の大きな違いは、「聴力に異常があるかどうか」です。
| 比較項目 | 感音性難聴 | LiD/APD |
|---|---|---|
| 聴力検査 | 異常あり(音が小さく聞こえる) | 異常なし(音の大きさは正常) |
| 原因 | 内耳や聴神経の障害 | 脳での音情報処理の障害 |
| 聞こえ方 | 音が歪む・小さい・こもる | 声は聞こえるが言葉として理解しづらい |
| 周囲の理解 | 「聞こえにくい」と説明しやすい | 「聞こえてるのに聞き取れない」が理解されにくい |
感音性難聴は、音の伝達経路の障害。
LiD/APDは、音を言葉として処理する脳の段階での障害です。
どちらも「話は聞こえているのに、意味が入ってこない」という共通のしんどさを抱えています。
診断名がつかない不安
私は感音性難聴と診断されており、「難聴なので聞き取りにくいです」と説明することができます。
それでも、聞き取れる場面と聞き取れない場面があったり、疲れてくると音がぼやけてしまったりすることなど、理解してもらうのが難しいと感じることも少なくありません。
一方、LiD/APDの方は「聴力は正常」と言われてしまうため、聞き取れない理由がわからず、説明も難しいのではないかと思います。
診断名がつかない不安は、私も経験があります。
私の場合は遺伝子検査によって原因がわかり、治療はできなくても「理由がわかった」という安心感がありました。
LiD/APDの方々も、「原因の見えにくさ」に苦しむことが多いのではないでしょうか。
共通点:言葉の意味が理解できない
| 状況 | 困りごと |
|---|---|
| 騒がしい場所 | 周囲の音と重なり、会話が聞き取れない |
| 早口の話 | 意味が入ってこない |
| 複数人の会話 | 話の流れについていけない |
| 電話 | 聞き返しが増える |
いくつか例を挙げてみましたが、LiD/APDでも難聴でも、「声は聞こえているのに、言葉が入ってこない」という状態が共通しています。
LiD/APDを知ることで、自分の難聴による聞き取りのしんどさを客観的に見つめ直すことができました。
LiD/APDの診断と支援の現状
日本では、LiD/APDを診断できる医療機関はまだ限られています。
また、教育現場や職場での理解も十分とは言えません。
それでも、最近は書籍やテレビ番組などで少しずつ取り上げられるようになってきました。
社会の中で「聞こえにくさ」にはさまざまなタイプがあるという理解が広がれば、LiD/APDの人にも、難聴の人にも、より優しい環境が整っていくはずです。
おすすめ書籍
- 『マンガ APD/LiDって何!?』(著:きょこ/合同出版)
- 『聞き取りが苦手すぎる男子の日常』(著:雨桜あまおう/KADOKAWA)
どちらも、LiD/APDの方の聞き取りにくさをリアルに描いた作品です。
感音性難聴の症状と重なる部分がとても多いので、「わかるわかる!」と共感しながら読めました。おすすめです!
「見えない聞こえの壁」を知ること
LiD/APDと感音性難聴。
違いがあっても、どちらも「見えない聞こえの壁」に日々向き合っています。
LiD/APDを知ることで、自分の聞こえを客観的に捉え、同じように悩む人の存在に気づくことができました。
周囲の理解が少しずつ広がれば、学校でも職場でも、生きやすくなる人が増えるはずです。
LiD/APDのことも、難聴のことも、もっとたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです。


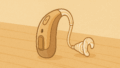

コメント