「もう一度言ってください」
「えっ?なんて言ったの?」
そんなふうに聞き返すことが多い私。音は聞こえているのに、言葉の意味がわからないーーそれは、音量の問題だけではありません。
私は中等度の感音性難聴で、補聴器を使って生活しています。学校という音の多い環境で働く中、さまざまな「聞こえづらさ」を感じています。その中でも特に大きな壁になるのが、「語音明瞭度(ごおんめいりょうど)」という感覚の問題です。
「聞こえているのに、わからない」
補聴器をつければ、音量はある程度カバーされます。「補聴器をつければ大丈夫でしょ?」と言われることもありますが、感音性難聴では、音量を上げても言葉が聞き取れないことがあります。
たとえば、こんな場面。
- 休み時間、子どもが少し離れた場所から「せんせい、◯◯が◯◯で…」と話しかけてくる。
- 職員室での打ち合わせ中、周囲のざわざわした声に紛れて、同僚の話がところどころ抜ける。
- 電話越しに「◯◯学校の◯◯です」と言われて、団体名や氏名が聞き取れない。
◯◯の部分の音は耳には届いているんです。音量も十分大きい場合もあります。
音は聞こえているのに、それでも意味がわからない。
そんな不思議で、もどかしい状況が日常のあちこちにあります。
語音明瞭度とは?
語音明瞭度とは、「どれだけ言葉を正確に聞き取れるか」を表す指標のことです。聴力検査の中でも、特に言葉の聞き取り能力を見るための検査で使われます。
私が以前受けた語音明瞭度検査は、ひと文字(たとえば「あ」「た」「ぱ」など)を音声で聞き取り、聞こえた言葉をそのまま検査係の方に伝えるというものでした。
簡単そうに聞こえると思いますが、難聴者にとってはすごく難しいんです。なぜかというと、感音性難聴は、音が歪んで聞こえることが多いからです。
私は特に高い音が苦手で、日本語の子音の聞き取りが難しいのですが、日本語は子音の聞き分けが大切な言語です。たとえば「さ」と「た」、「か」と「が」などの区別がつきにくくなると、会話の内容が曖昧になります。
語音明瞭度検査を受けた時も、「は」か「ま」か、「た」か「ぱ」かなどで迷うことが多く、勘で答えてしまったことが何度もありました。ちなみに前回受けた時の正答率は、補聴器なしで6割〜7割、補聴器をつけてやっと7割〜7割5分ほどでした。
「音をキャッチする耳」は働いていても、「キャッチした情報を意味のある言葉として脳に伝えるまでの経路」のどこかに問題があると、このような聞こえ方になるそうです。
言葉の聞き間違い
語音明瞭度検査の時のように、たったひと文字ずつでも聞き間違いが多いので、人との会話になるとさらに大変です。日常生活を過ごす場所はたいてい検査室のように静かではなく、周囲の喧騒でさらに聞き取りが難しくなります。
- 「ご飯だよ」と言われたのに「おはよう」と聞き間違える。
- 「教室」と言われたのに「給食」と聞こえてしまう。
こんなとんちんかんな聞き間違いもしょっちゅうです😂
難聴者はこの不完全な聞こえを、表情・口の動き・前後の文脈といった「視覚情報」や「推測」で補っています。
虫に食われて穴だらけの本を読んでいるような、外国語のリスニング問題を解いている時のような…説明が難しいですが、毎日頭の中で聞き取りパズルをしているようなもので、たくさん会話をした日はものすごく疲れます。
大人になって学校で働くようになって改めて感じるのは、学校という場所が、難聴者にとって決して過ごしやすい環境とは言えないということです。私は今でこそ視覚情報を活用したり、周囲に助けを求めたり、ときには聞こえなくても割り切ったりすることができるようになってきました。でも、難聴の子どもたちは、そうした手段を持たないまま、毎日とても大変な思いをしているのではないかと思うのです。
子どもとのやりとりにも影響
教室では、子どもたちは小さな声やあいまいな発音で話すことも多く、「語音明瞭度」の壁が大きく立ちはだかります。
「せんせい、◯◯が◯◯したの!」と報告してくれるけれど、肝心の主語や動詞がうまく聞き取れない…。
そんなときは、
- 「どこで?」
- 「だれが?」
- 「もう一回、ゆっくり言ってくれる?」
と丁寧に聞き返すことが必要です。
でも、子どもたちは優しくて、何度でも話し直してくれることが多いです。だから私は、正直に「聞こえにくいからもう一回教えてね」と伝えるようにしています。
補聴器があっても、限界がある
補聴器は、音を大きくする道具。でも、語音明瞭度を改善することは難しいです。
視力の低い人が眼鏡をかけるとくっきり見えるのと、同じようにはいきません。
つまり、「音は大きくなったけど、やっぱりわからない」という状況が起こりやすい。
そのため、騒音の多い環境や電話、マスク越しの会話などは、よりハードルが高くなります。
コロナ禍で苦しんだ難聴者はたくさんいたと思いますが、マスク生活がつらかったのも、「口元が見えない上に、声がこもって聞き取れない」からでした。
伝えること、配慮してもらうこと
「聞こえていない」のではなく、「聞き取れていない」ーーこの違いを、もっと多くの人に知ってもらいたいと思っています。
私自身も、最初は「ちゃんと聞けなくて申し訳ない」という気持ちが強く、なかなか難聴のことをオープンにできませんでした。でも、伝えたことで助けてもらえた経験が何度もあります。
難聴は「見えにくい障害」です。でも、知ってもらえたらきっと、やさしい配慮が広がっていくはず。私も、聞き返す勇気を持ち続けながら、子どもたちと安心して過ごせる教室づくりを目指していきたいです。
おわりに
語音明瞭度ーーそれは、「聞こえる」ことと「わかる」ことの間にある、大きな壁。
感音性難聴の私にとって、それは毎日の暮らしや仕事の中で、何度も向き合うテーマです。
このブログが、「聞こえにくさ」について考えるきっかけになったらうれしいです。
読んでくださって、ありがとうございました。


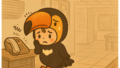

コメント