電話対応のプレッシャー
「電話が鳴るのが怖い」
これは、私が長年ずっと感じてきた気持ちです。
電話が苦手な難聴の方は、本当にたくさんいらっしゃると思います。
私は中等度難聴の教員です。補聴器を使って生活しています。
普段の会話は何とかなることが多いのですが、電話となると話は別です。
「電話って、こんなに怖かったっけ?」
「電話の声って、どうしてあんなに聞き取りにくいんだろう?」
相手の顔は見えない、口の動きも見えない、身振り手振りもない。
しかも、学校にかかってくる電話や、教室にある内線にかかってくる連絡は、たいてい“急ぎの用件”ばかりです。
- 「○○が熱を出したので、欠席させます」
- 「○年○組の保護者から相談の電話が入っています」
- 「怪我をした子がいるので、至急保健室へ来てください」
…これ、全部うまく聞き取れなかったら大変なんです😭
聞き返しても、相手が早口だったり、ざわざわした教室や職員室だと、さらに聞き取りづらくなります。
結局何度も聞き返してしまい、相手に不審がられたり、申し訳なさそうにされてしまうことも。
校内の内線の場合は、あまりに聞き取れなくて、かけてきてくれた人のところに直接ダッシュすることもあります😂
鳴らないで!と祈る日々
私にとって、学校での電話対応は、ある種の“試練”です。
こちらから保護者の方にかける場合は、大抵、何らかの報告や確認がほとんどなので、意外と話しやすいことが多いです。
学校での子どものエピソードで楽しく談笑できることもあります。
苦手なのは、相手がどこの誰かもわからない、突然かかってきた電話に出ること。
とくに聞き取りづらいのが、所属や氏名です。小学校には、保護者からだけではなく、教育委員会、他の小学校や中学校、幼稚園、保育園、教材や校内設備に関わるさまざまな業者、などなど、他にもいろいろな方から電話がかかってきます。
「○○教材の○○です」
「○○学校の○○です」
――聞き覚えのない固有名詞を聞き取るのは本当に難しい!
それでも懸命に聞こうとしますが、聞き返せるのは一度に2回が限度。
3回目になると、ものすごく冷や冷やします😭
私がこれまで働いてきた小学校の職員室では、管理職の先生や事務職員の方が出てくださることも多かったですが、その方たちが出られないときは、基本的に“近くの人が取る”のが暗黙のルール。
電話機のそばを通るたび、心の中で「鳴りませんように」と祈ってしまいます。
電話が鳴っても
電話のベルが鳴るたび、落ち着かない気持ちになります。
聞き取れなかったときの申し訳なさや、分からないまま話が進んでしまう怖さは、きっとこの先もしばらく消えないと思います。
私は今日も、「電話よ、鳴らないで!」と祈りながら働いています。
でも最近は、「苦手なことは苦手」と割り切ることも必要だと感じるようになりました。
職場で難聴のことを伝えられる方は、「電話対応が苦手です」と周りの方に伝えて、配慮してもらうのもいいかもしれません。
もちろん、それが難しい場合もあると思いますが…。
難聴者も引け目を感じずに働ける職場が、もっと増えてほしい。
そして電話が鳴っても、
「ごめんなさい、私は電話が苦手です!取れません!」
――そう、堂々と伝えられる自分に、いつかなりたいなと夢想する今日この頃です😂



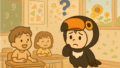
コメント