カクテルパーティ効果、という言葉をご存じでしょうか?
なんだか楽し気な言葉ですよね。私ははじめて聞いた時、お酒に酔ったときのようなふわふわした気持ちになることかな?と思いましたが、実はそうではありません。
みなさんは、にぎやかな場所(例えば学校、BGMが流れる飲食店、人の話し声が多いカフェや居酒屋、商業施設など)でも、自分の名前を呼ばれるとハッと気づいたり、興味のある話題に自然と耳が向いたりすることはありませんか。
これが「カクテルパーティ効果」と呼ばれる現象です。
たくさんの音が飛び交う中でも、意識しなくても、自分に関係する話題や必要な声を“選び取る”脳の働き。
でも、難聴者にとってこの「必要な音を選び取る」ことは、実はとても難しいんです。
難聴ではない人でも、騒がしい場所では話が聞き取れないことがあると思います。しかし、難聴者はカクテルパーティ効果が働かないことで、さらに聞き取りが困難になります。
人の声を「選ぶ」力が働きにくい
カクテルパーティ効果は、音の聞き分けを支える脳の仕組みの一つです。
でも難聴があると、その効果がうまく働かないことがあると言われています。
だから、私は聞こえにくさだけでなく、「音を選ぶこと」にも苦労しています。
周囲の音と、相手の声の境界があいまいになる。
周囲の雑音も、話し相手の声も、すべてまざってしまって、意識しても必要な情報だけを聞き取ることが難しい。
そのため、近くで自分に関係ある話をされていても気づけなかったり、会話のテンポについていけず、ポツンと取り残されたりすることが、たびたびあります。
にぎやかな場所での会話がしんどい
私が特に苦手なのは、BGMが大きめに流れているカフェや、にぎやかな居酒屋。
学生の頃は、友人と集まって食事に行っても、話についていけないことがよくありました。
周囲の音や声に言葉がかき消され、相手が何を言っているのか分からない。
特にお酒が入ると自然と会話のテンポが早くなりがちです。
周りが楽しそうに話している雰囲気をこわしたくなくて、聞き返すのも気が引けて、聞き役に徹し、聞き取れていなくてもうなずいたり笑ったりしてごまかすばかり。
楽しそうなふりをしながら、実は話の中身がほとんど分かっていなかった――そんな場面が何度もありました。
聞き取れていないのに、聞こえているふりをするのはよくないなと思いつつ、今でもつい同じようにしてしまうことがあります。
自然と、大人数での集まりより、静かな場所で、2人や3人で過ごす方が落ち着くようになりました。
学校の中で
学校では、子どもとの会話が重要な教員という仕事。
以前「発表が聞こえない」という記事でも書いたのですが、授業中に困ることがたくさんあります。
しかし授業以上に、聞き取りにエネルギーを使うのが休み時間です。
休み時間は、子ども達が教室の中や廊下で自由に話しています。
机やいすががたがた鳴る音や、校内放送の音なども加わります。
そんな中で、
- 「先生!○○が○○でね!」と楽しそうに教えてくれたり
- 「○○さんに○○て言われた。」と悲しそうに相談されたり
特に子ども同士の喧嘩やトラブルは、聞き間違いがあってはいけないので、聞き取れなかったから聞き流す、というわけにはいきません。
何度も聞き返して、話の流れが合っているか確認しながら進めていきます。
特に低学年の子は、要点を簡潔にまとめて話すことが難しいです。
中には記憶が曖昧な子や、話しているうちに言っていることが変わる子、自分のしたことを隠そうとする子もいるので、話の聞き取りに休み時間丸々かかってしまうことも珍しくありません。
次の授業の準備や、宿題の丸付け、連絡帳への記入など、休み時間にも様々な仕事がある中での雑談や相談。
小学校は、基本的にクラス担任が一人でそれらすべてに対応する必要があるため、毎日がまるで嵐のようです。😂
放課後の、職員室のざわめきもなかなかのハードモードです。
子どもたちが下校してやっとひと息つける、と思っても、次の日の授業の準備や事務仕事が待っています。
教室から職員室へ戻ると、近くの席で同僚が話していたり、誰かが電話で話していたり、印刷機が動いていたり……
そんな中で「ねぇねぇ、ちょっといい?」と声をかけられた時は、一気にそちらに全神経を集中させます。
「え?今、なんて言ったんだろう?」と必死で耳をすませ、文脈を推測しながら返事をします。
電話応対も同じです。
周囲の雑音が混ざると、相手の声が聞こえにくくなり、何度も聞き返してしまうことも。
電話を親機から子機に切り替え、できるだけ音がしない職員室の隅や、廊下に移動して話すこともあります。
短時間でも、頭も耳もフル回転。
一日が終わって家に帰ると、精魂尽き果ててぐったりしてしまうことがよくあります。
妻からはよく「屍になってる」と言われています。😂
恐怖のグループワーク
教員の仕事は、授業や子どもとの関わりだけではありません。
放課後や長期休暇中など、校内外の研修にたくさん参加します。
その中でも特に困るのが、グループワークの時間。
会場内にいくつものグループができ、それぞれが意見を交わす――そんな状況では、周囲の話し声が一斉に耳に飛び込んできて、誰が何を言っているのか、聞き分けるのがとても難しくなります。
「今、目の前の人が話している声」と「となりのグループの声」が重なって聞こえる。
気がつけば、発言者の口元をじっと見て、なんとか意味を補おうとしている自分がいます。
でも集中すればするほど疲れて、後半は内容がほとんど入ってこないこともよくあります。
特に、校外の研修では、はじめて会う方とグループになることがほとんどなので、私の難聴のことを知らない人ばかりです。
その中で司会や書記を決め、最後にグループごとに発表する、という流れが定番です。
補聴器をつけていなかった頃は、周りに言いづらく、心の中で悲鳴をあげながら司会や書記を担当することもありました。
しかし、話し合いの制限時間がある中で司会が何度も聞き返すと、話が滞ってしまいます。書記がきちんと記録をとっておかないと、発表する人が困ります。
今は、話し合いがはじまる時に、自分の難聴のことを伝え、司会や書記からはずしてもらえるようにお願いしています。
申し訳ない気持ちでいっぱいですが、円滑なグループワークのためと割り切って、考えすぎないようにしています。
それでも考えちゃうんですけどね。😭
カクテルパーティ効果が働かない時、いろいろ
ほかにも、カクテルパーティ効果が働かない場面はいろいろあります。
- 車の中:走行音やラジオ、音楽で会話が聞き取りにくいです。特に高速道路は難しいです。
- 家の中でテレビがついている時:テレビを集中して見ていなくても、音と声が重なって聞き取りにくいです。
- 理容院・美容院:他のお客さんの話し声やBGMで聞き取れません。話しかけられても、相槌や愛想笑いで乗り切るしかなく、逃げ出したくなります。
「あの人、静かだね」には、理由があるかもしれない
カクテルパーティ効果がうまく働かないと、ざわざわした場所では、自然と“聞くこと”をあきらめてしまいがちです。
結果的に、会話に加われない。話しかけるのをためらってしまう。
話すのが好きな人でも、「おとなしい」「控えめ」「人見知り」なんて思われたり…。
でもそれは、単にその人の性格というわけではなく、“カクテルパーティ効果”が働かないことも、理由の一つかもしれません。
私も大人数での雑談が苦手です。元々の性格なのか、カクテルパーティ効果が働かないからなのか、もうわからなくなってきてますが。😂


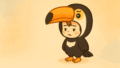

コメント