はじめに
私は中等度感音性難聴があります。前回の記事夢を諦めた10代の葛藤。おはしの物語(2)難聴と職業選択では、高校生の頃に消防士や海上保安官を志すも、難聴により聴力基準を満たせず、あきらめざるを得なかった経緯を書きました。まずはそちらを読んでもらえると話の流れがわかりやすいと思います。
今回は、夢をあきらめた後の進路と、難聴の影響が次第に大きくなり、苦しかった大学生の頃のことについて書いてみようと思います。講義がまったく聞き取れず、留年や休学を経験し、心が折れそうになった大学生活。これは、そのときの話です。
読んでもらえるとうれしいです。
決められなかった道
高校生になり、消防士や海上保安官になりたいという夢をあきめた私。結局その後、代わりの道を決めることができず、受験シーズンになっても勉強が手につかずにいました。
絶望していたわけではありません。この頃の私は、割と楽天的で引きずらないタイプでした。高校3年生になった頃には完全にふっきれており、むしろ興味のあることが次々と出てきていました。
留学したい、獣医になりたい、美容師になりたい。ころころやってみたいことが変わって、それを思いつくまま、全て高校の担任にも伝えていました。初めは真剣に聞いてくれていた担任も、次第にあきれ始め、「あなたのことよくわからない。」と言われてしまいました。😂
今思えば、いろんな夢を語るうちに、自分でも本当は何がしたいのかわからなくなっていたのだと思います。
今決めきれないなら、四年制大学に進む方がいい、学部はつぶしがきくところ!という担任のすすめに従い、あっさり受験を決めました。😂ちなみに教育学部ではありませんでした。
大学で受けた難聴の洗礼
なんとか大学受験を乗り越え、高校を卒業。大学は実家から通うのは難しい場所だったので、一人暮らしを始めることにしました。
その頃には、消防士や海上保安官への憧れはもう遠い過去の話。新しい生活にわくわくしていました。
新入生オリエンテーションに参加し、何人か話ができる友達もできたところで、いよいよ講義が始まりました。ところがそこから、状況が一変しました。
当時軽度難聴だった私は、小学校、中学校、高校での授業ではそれほど大きな支障を感じていませんでした。はきはき話す先生が多く、丁寧に板書をしてくれたからです。時々聞き間違いや聞き逃しをすることはありましたが、問題なく授業についていくことができていました。
ところが大学はまるっきり違いました。大きな講義室、早口でぼそぼそと話す先生。マイクを通して声が大きくなっても、肝心の「言葉」が聞き取れない。感音性難聴の私にとって、「大きい声」=「聞き取れる」ではないからです。
当時私が在籍していた学部では、全く板書をしない先生、プリントやスライド資料をいっさい使わない先生、90分間ひたすら話し続ける先生がほとんどでした。
大げさではなく、話の内容が9割以上聞き取れないまま、講義が1コマ終わってしまうこともたびたびありました。
講義についていけない不安。まわりの学生が笑っているのに、何が面白かったのかすらわからない疎外感。内容がわからない言葉を毎日何時間も呪文のように聞き続けること。毎日が苦痛でした。
1年生の間は一般教養科目が多く、なんとかなりましたが、2年生になって専門科目が多くなると、もうお手上げでした。専門科目には、講義に出席したからといって出席点はなく、1年に1回、学年末の試験だけで成績をつける科目がたくさんありました。
「何のために大学に通っているんだろう。」
講義に出ることに意味を見いだせなくなった私は、だんだん大学から足が遠のくようになりました。
結局、単位を落としてその年は留年してしまいました。
「聞こえない」という現実が、これほどまでに自分の生活を左右するのか、と打ちのめされた日々でした。
高校まではそれなりに自信があった自分。大学でもうまくやっていけると思っていました。そんな自信が、跡形もなく崩れていきました。
心が落ち着かない状況が続きました。
それでも、新しい学期が始まると、気持ちを入れ替え、今度こそ頑張ろうと気持ちを奮い立たせました。毎回予習をして講義に臨み、懸命に話を聞き取ろうとがんばりました。
ですが途中でエネルギーが続かなくなり、また講義を休み始める。単位を落とす。そんなことを何度も繰り返し、悪循環に陥っていました。
我ながら不器用すぎたと思います。
試験だけで単位がもらえるなら、友達に頼るなり、先輩に聞いて過去の試験傾向を探るなり、何かしらできることがあったと、今では思います。しかし、当時の私はどれもすることができませんでした。
試験は自分の力で乗り越えるもの、という考え方がしみついていて、正直に言うと、周りに助けを求めるという考えが全く頭に浮かびませんでした。
また、高校までは聞こえのサポートなど一切受けてこなかったので、聞こえのことを大学に相談するという選択肢もいっさい浮かびませんでした。
10代の頃に持っていた自信は、粉々に砕け散りました。
高校までとあまりに違う自分の姿を受け入れられず、眠れない夜が続きました。
それまで人と関わることも苦手ではなかったのですが、だんだん人と話すことも怖くなってきてしまいました。
役に立たない耳をいっそのことひきちぎってやりたい。自分の人生なんてもうだめだ……
と、暗い気持ちで毎日思い詰めていました。
生活費を稼ぐためにアルバイトだけは続けていたのですが、そちらにもなかなか馴染めませんでした。
抑うつ状態のようになってしまった私は、両親とも相談し、一度立ち止まって考えてみる方がいいと思い、1年間休学することにしました。出口のないトンネルに入りこんだようだとよくいいますが、あの頃の自分はまさにそういう状況でした。
気持ちを立て直すのに、長い長い時間がかかりました。今でもいろいろ悩むことはありますが、あの頃が人生で一番しんどかったです。
生まれてはじめての補聴器
1年間の休学を経て、自分でも驚くほど気持ちが前向きになりました。
それまでは、行かなければいけないところに行っていないという罪悪感でいっぱいだったのですが、休学中はその罪悪感からも解放され、ゆっくり休めたのがよかったのだと思います。
私は、大学に戻ることを決めました。でも、講義が聞き取れない問題は残ったままです。そこで、生まれて初めて、補聴器の購入を考え始めました。
しかし、周りに補聴器を使っている知り合いのいない私は、補聴器については何もわからず、とりあえず補聴器店へ。
驚いたのはその価格です。両耳で数十万円以上することも珍しくなく、私のように、軽度〜中等度の難聴で障害者手帳を持っていない者には、公的な補助はほとんど出ません。自治体によって条件は異なるものの、子どもや高齢者に比べて、働き盛りの年齢の難聴者は支援の対象になりにくいのです。
それでも自分には絶対に必要だと思い、いくつか試して購入しました。
補聴器をつけ始め、たしかに耳に入ってくる音は大きくなりました。
虫の声や体温計の電子音など、子どもの頃には聞こえていたものの、いつの間にか聞こえなくなっていた音が、また聞こえるようになったことにはとても感動しました。
でも、それまで聞き取れなかった言葉が聞き取れるようになったかというと――正直あまり違いを感じられませんでした。思ったほど「言葉の明瞭さ」は向上しなかったのです。
大学の講義でも数か月使ってみたのですがやはり聞き取れず。人生で初めて手にした補聴器はあまりしっくりこず、結局、使わずにしまっておくことが増えていきました。
それでも、なんとか講義には出席し続けました。
ちなみに復学した時には、入学した頃にできた友人達はもう卒業しており、一人で大学に通う日々でした。相変わらず講義が聞き取れない状況は続いていましたが、そこはもう聞こえないものと割り切り、参考書などを使って自習の時間にあてました。
復学から3年間、楽ではありませんでしたが、なんとか必要な単位をとって卒業することができました。
我慢強く見守ってくれた両親には感謝しています。
おわりに
高校では職業選択、大学では講義──思い通りにいかず、人生で特にしんどい時期でした。
今思えば、難聴の症状だけではなく、自分の不器用さも大きな原因だったと思います。
特に大学時代は、こんなはずじゃなかった、こんなこともできない自分はだめだ、と、いつも自分を責めるようになってしまっていました。
周りに助けを求められていたら、もっと早く立ち直れていたかもしれません。
それでも、休学期間をはさみ、0か100かの思考を手放すことで、少しずつ自分を許せるようになっていきました。
さて、無事卒業できた私ですが、特別な資格も経験もなく、あるのは留年と休学の分、年齢だけ重ねた自分…すでに20代後半でした。😂
次回は、そんな私が卒業後にどんな道を選んだのか、お話ししたいと思います。


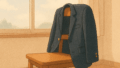

コメント