コロナ禍から数年が経ち、ようやくマスクを外して過ごせる日常が戻ってきました。
新型コロナウイルスによって、学校の風景は大きく変わりました。
子どもたちは全員マスクをつけ、教室の窓は開け放たれ、そして換気扇がブーンと音を立てて回っています。
これらは、感染対策としてとても大切なことでした。
けれど、私のように難聴のある人間にとっては——
難聴、マスク、換気扇という「三重苦」の中で、もともと苦労していた日々のコミュニケーションが、さらに難しくなっていきました。
◆ マスクで口元が見えない
私にとって、相手の口の動きを見ることは、大きな手がかりになります。
でも、マスクでその情報が遮られてしまいました。
子どもが話しかけてきても、「口のかたち」から意味を推測することができず、
たとえば「先生、トイレ行ってきていいですか?」が、ただの「モゴモゴ…」にしか聞こえないこともあります。
聞き返すと、「さっき言ったのに…」と悲しそうな顔をされることもあり、胸が痛みました。
中でもつらかったのは、マスクをした子が後ろから私を呼んでくれていたのに、気づけなかったときです。
廊下や教室で名前を呼ばれていたのに、私は気づかずに通り過ぎてしまって…。
「先生、呼んだのに…」と、あとから寂しそうに言われたり、少しイライラした様子で言われたり——
「ごめんね」と謝ったことは、一度や二度ではありません。
謝罪スキルだけは日に日に上達していきました😭
◆ 換気扇のブーンという音
もうひとつの“壁”が、教室の換気扇の音です。
学校にもよると思いますが、私が勤めていた小学校の換気扇は、
「いったいいつから使ってるの?」と思うくらいのレトロな一品で、回すとそれなりに大きな音がしました。
この「ブーン」という低く響く音が、聞き取りをさらに難しくするのです。
まるで、目に見えない“音を遮るフィルター”がかかっているような感覚でした。
◆ 扇風機やエアコンも“音の壁”
夏になると活躍する扇風機やエアコンの音も、この“音のフィルター”をさらに厚くします。
扇風機の「ウィーン」、エアコンの「ブォーッ」という送風音。
これらが重なると、教室全体にBGMが流れているような状態になります。
子どもたちの声が遠く感じたり、音が反響して方向がつかめなかったり。
とくに、複数の子達が同時に話し始めると、何ひとつ聞き取れず、もうお手上げ。
毎回頭を抱えていました😭
◆ 難聴だけが理由じゃない
「聞こえないって、大変ですね」
「補聴器をつけてても、わかりづらいんですね」
そんなふうに声をかけてもらうこともあります。
でも、私が思うのは「難聴の人だけが困っていたわけじゃない」ということです。
マスク越しの会話や、環境音の大きい教室は、難聴の有無に関係なく、
すべての子どもたちや先生たちにとって、大きな負担だったのではないでしょうか。
◆ 小さな心配り
子どもの言葉がどうしても聞き取れなかったときには、
「ごめん、紙に書いてくれる?」とお願いすることがあります。
すると不思議なことに、子どもたちは自然と「書いて伝える」ことに慣れてきます。
そして、「先生、聞こえてないかも」と気づいたときには、
少し声を大きくしたり、近くまで来て話してくれたり。
そんな小さな心配りが、教室の中で少しずつ広がっていくのを感じました。
◆ 伝え方をかえれば
コロナ禍で、学校はたくさんの困難に直面しました。
でもその一方で、「どうやったら伝わるか」を考えるきっかけにもなりました。
声が届きにくいとき、身振りや表情、文字や絵を使って伝えようとする子どもたち。
そんな姿に、私は何度も助けられてきました。
「伝え方をかえれば、届く言葉もある」
この経験を、これからも忘れずにいたいと思います。
そして願わくば、全国の学校が、音の静かな換気扇や扇風機に買い替えてくれますように。🤣


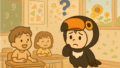

コメント